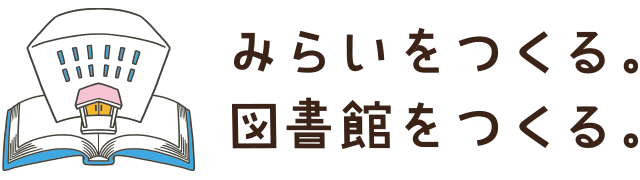図書館を知る
多くの方に興味を持っていただけるように、図書館を紹介します。
オンライントークイベント 「本にかかわる人の本にかかわるはなし」 vol.1 / 及川 卓也さん(後編)
岩手県花巻市の「新花巻図書館計画室」では、本にまつわる方々を招き、本のある空間や暮らしについて皆さんと一緒に考えていくため、全3回にわたってお送りするオンライントークイベントを開催しました。 令和3年11月11日に、株式会社マガジンハウス 広告局局長・クロスメディア事業局局長・コロカル統括プロデューサーであり、岩手県一関市出身の及川 卓也さんをお招きし開催したイベントの様子を2回にわたって公開します。
この記事は後編です。前編は次のリンクから読むことができます。
オンライントークイベント「本にかかわる人の本にかかわるはなし」 vol.1 / 及川 卓也さん(前編)
言葉の海を泳ぎ、知の森を彷徨う楽しみ方
及川卓也さん(以下、及川):ここまでの話を整理しますと、図書館というものを私なりに捉え直していくと、知的エンターテイメントとしての読書機会を提供する場所だったり、子どもたちに読書の楽しさや面白さを感じていただくような教育的な場所だったり、言葉や本の価値がきちんと提供されていくような出会いの場所なのかなと思います。本屋さんと大きく違うのは、新刊だけを配架コーナーに置くのではなく、きちんと裏側に資料をアーカイブしていてそれに出会えること。歴史を遡って本と出会えたり、さまざまなジャンルの情報と出会えるアーカイブ機能を持っていることも大事だと思います。学びや体験の場所と機会を提供するスペースを持つだけでなく、本の読み聞かせや読書会、さらにもう少し幅広く文化的な地域を知る企画などを実施して機会を提供する場所になってもいいのかなと思います。そして、地域の図書館に必要なのは、地域資料の収集と提供です。きちんと図書館に地域の資料が集約されて、それが長く閲覧できるようになっているというガイダンス機能や、データベース機能として検索をする時に本を引きやすくなっていることも大事です。配架された本を見て取るだけではなく、さまざまな活用方法を持っているということ。それが大事なのかなと思います。
-1024x497.png)
つまり、図書館は、本や言葉との偶然の出会い、いわゆる「セレンディピティ」のある場所になっていくことが必要なんじゃないかと。今まで知らなかった本に出会えたり、知らなかった世界に興味を持ったり、そういう場所になっていくといいんじゃないかと思います。時間を遡って歴史的な本と出会い、それを現代的な意味に捉え直して、新しい可能性や気づきを得ていくこともできるような。「言葉と知の海や森を泳ぐ彷徨う場所」。その場所に行って何かと出会う、それを読み込む、その中で次の本に行き着く。そういう「海を泳ぎ、森を彷徨う」ような行為が促される場所であるのがいいんじゃないかと。図書館は人が育つ場所になっていくのが素晴らしい形になるんじゃないかなと思います。
話はずれるかもしれませんが、雑誌編集者がインターネットが普及する前によく使っていた「大宅壮一文庫」というものがあります。例えば何か特集を組んだり取材する人を調べたりする時に、人名やキーワードをFAXで送るんですね。すると「こういう資料がありますよ」というのがFAXで届いて「じゃあこれとこれのコピーを送ってください」と送ると、それがFAXで届く。そういった我々の情報収集のサポートになってくれた図書館があるんです。大宅壮一さんという方は、かつてジャーナリストとして活躍された方。「本は読むものではなく引くものだよ」とおっしゃっていて、膨大な量の雑誌を多く収集されてきました。ご自身がコレクションしてきたものが1つの文庫になっているんです。雑誌が1万2700種類、80万冊。それらがここに全て集約されていて、まさにここは、「森を彷徨う」とか「海を泳ぐ」とか、そういう楽しみ方ができる場所になっているなと。一方で検索機能を持つことによってデータが収集されて引きやすくなっているんです。
本が「人のように」、というと変かもしれませんが、無機質なものではなく、もう少し息吹を持っているものという実感があると面白いのかなと思います。今はパソコンやスマホ、動画を簡単に見られる時代で、Webの記事だと自分の知りたいことを検索して読んだらそれで終わりということになりがちです。しかし、本との向き合い方、その時間、ページをめくっていくことなどを味わう楽しさを知ってほしいと思っています。1ページ1ページめくっていくことによって自分が読みたかった内容の先にまだ自分が知らなかったことに出会えるような、偶然の出会いが待っている。ページをめくるというのは一つの冒険であるという感覚を持って雑誌や書籍に向き合っていただけると、すごく楽しくなると思います。
本棚は生きている
僕にとって、そういうことを考えさせられる場所だったのが、大宅壮一文庫と対極にあるような「いちのせき 文学の蔵」です。一関に、蔵造りの建物が並ぶ昔のお屋敷の跡地を引き継がれてレストランや販売所を運営されている有名な酒蔵「せきのいち酒造」があります。この敷地の隅に「日本一小さな文学館」としてあるのがいちのせき文学の蔵で、一関にゆかりのある作家の方々の本が展示されているんです。もちろん地元の作家を知るという入り口としての機能がある場所ですが、特筆すべき点は、蔵という場でありながら、非常に活動を行う運動体だったということです。
『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室 文学の蔵 編』という書籍があります。先ほどの蔵のある場所に井上ひさしさんのお母様がお仕事で滞在されていて、井上さんも幼少期ここで育ったそうです。そのご縁で、文学の蔵が主催する作文教室に講師としてお見えになり、本当に丁寧に何日もかけて文章教室を開いたんです。その時の作文の添削のプロセスを有名出版社から本にして、文庫にもなっていて、10万部以上売れる本となりました。この活動をしていたのが文学の蔵だったのです。本を巡って活動していく場所として文学の蔵は機能していて、非常に重要な存在意義のある場所でした。図書館がそのような場所になる可能性もひとつ考えられるのではないかなと思います。
文学の蔵では会報誌を作っていて、3号で父の追悼号をやっていただいたんです。父は文学の蔵にも関わっていたので、会員の皆様のご好意で追悼号が出て、その時に私も一文を寄せさせていただきました。抜粋ですがご紹介させていただきます。自分の文章を紹介するのも恐縮ですが、今回のテーマに合ったものだったので。
子どもの頃から、父の本棚を見てきた。本棚は生きているとつくづく思う。漱石や太宰などの近代文学群、戦後文学の現代作家の小説、プロレタリア文学の戦前と戦後の作品群、文学表現に関する本、海外文学、哲学、美術領域の書籍や画集。父の関心領域がややもするとむき出しに顔を覗かせていた。
子どもの頃、父の本棚から抜き出して、大人の世界を覗くこともした。官能的な表現にドキドキしたり、小難しい文章をわかった気になったりと、刺激的だった。
父の本棚は、長い時間をかけて蓄えを増殖し続けた。それは、単に数が増えていくのでなく、父の関心の遠近が見えた。
(中略)
父が亡くなり、この最後の作品にまつわる書列が彼の机から本棚に収まると、この本棚の増殖は止まる。しかし、私にはそれが死だとは思われない。
岩手の地方都市の小さな家の片隅の書棚であるが、父の知の生態系は呼吸しているような気がする。小さな本の森が、残された家族や、もしかしたらこれから訪れるゲストに息を吹きかけてくれるような気もしている。
(及川卓也「最後の書列」『ふみくら』3, 2019, 70-73)
僕の感覚としては、父の本棚は、今後父が買った本によってどんどん増えていくわけではない。でも時々本が誰かの目に触れたり、孫に読まれたり、そういったことによって本棚は生き続けていくんじゃないかという思いを込めて書いた文章です。
先ほどの言葉の意味「知の森へ」というのにつながるのですが、図書館というのは本が並んでいるだけではなく、知の生態系のような、生きている場所として存在している、あるいは存在させていくというのが重要なんじゃないのかなと考えています。利用する人たちが森を彷徨うように、海を泳ぐように、図書館を回遊してみる。それが実現するとますます図書館の価値が深まっていくし、本を読むだけでなく、運動体のような生きている存在として図書館があり続けるのは、まちにとって大事なことなのかなと思っています。
専門的でない拙いお話で恐縮ですが、編集者として、本に触れてきた人間として、今日はこういうお話をさせていただきました。ご静聴、ありがとうございました。
-1024x498.jpg)
本のある場所の居心地の良さの大切さ
高橋信一郎さん(以下、高橋):ありがとうございました。無茶振りをした上に年下の僕が言うのも恐縮ですが、すごく面白い話でした。ありがとうございました。
及川:いやぁ、無茶振りでしたね(笑)
高橋:及川さんは「専門的じゃない」とおっしゃったんですけど、新しい図書館を作るにあたって本に関わってきた方のお話を聞かせていただきたかったので、ありがとうございました。
コメント欄に、いくつか質問が来ています。花巻の方です。「及川さんが読書を習慣にしたきっかけはなんですか。読書が習慣になっていない子どもたちに、図書館へ足を運ばせるような図書館の機能にはどんなものがありますか」。
及川:僕が継続的に読書をするようになったのは、シャーロックホームズシリーズと出会ったからなんですよ。30〜40巻くらいあって、毎月一冊読むようになって、どんどん読んでいきました。推理小説なのでエンターテイメントとして読みやすいのと、推理やプロファイリングの論理的な思考が数学の役にも立ったなと。あとは課題図書ってあったじゃないですか。それを読んで感想文を書いて、ちょっと褒められて、また感想文書いてってしていました。「読む」と「書く」の連携ができて、それでトントンと読んでいったというのはありますね。
高橋:わかります。僕も土器の本とかを読んだりしてドキドキしていたので。面白く読んでいた記憶がありますね。
及川:あと、図鑑も好きですね。
高橋:楽しいですよね。動物の図鑑だったり、電車の図鑑だったり。いろんなものがありますもんね。
及川:きっかけはそれぞれあると思うんですけど、それが次の本を読みたくなるようになっていくようなものに出会うと継続性も出てくるのかなと思いますね。
高橋:なるほど。ありがとうございます。まだ時間があるのでもう1つお願いします。「首都圏ではなく地方の新しい図書館だからこそ期待したいことはありますか?」
及川:地域や福祉のメディアをやる中で一つキーワードになっているのが「居場所」です。自分の居心地のいい場所を見つけることってすごく大事だと思っていて。都市部って、お店とか場所はたくさんあるんだけど、なかなか人も多くて居場所が見つかりづらいとか、騒がしいとか、ありますよね。今日は紹介しなかったのですが、長野県小布施町で、「まちとしょテラソ」という新しいタイプの図書館があって。普通の図書館は私語禁止なんですが、割と自由に会話ができて子どもたちが騒いでいいよ、という場所なんです。読書する方のために静かな部屋もあると思うんですけど、「静かに」という規制を緩くして、「居場所」として子どもたちが来やすかったり、一緒に活動しやすかったりということを実現していて新鮮でした。例えば中学生とか高校生が何人かで集まって復習や予習をしたりするような場所でもあるので、居場所としてまず親しんでもらって、そのさきに本との出会いが始まっていくような、そういう場所になるといいんじゃないかなと思います。
本を通じて新しい対話が生まれる場所
高橋:最後に、及川さんの考える未来の図書館ってどんなものだと思いますか?
及川:難しいですね……。
高橋:感覚的で構わないです。先ほどの「居場所」のお話がすごく刺さっていて。これからの図書館にはいろんな可能性があると思うのですが、及川さんが選ぶ未来の図書館は、やっぱり「居場所」がキーワードになりますか?
及川:今、都市部では世代間が違う人が交流することもなくなったり、趣味が合う人たち、いわゆる属性が同じ人たちが集まったりしていると思うんですが、地域って伝統芸能をおじいさんが若者に教えるとか、そういった世代間の交流もありますよね。世代や属性が違う人たち、立場とか感覚が違う人たちが出会って何か話ができるような出会いの場所が重要な気がしていて、出会いの機会を本によってどういう風に作れるか、ですかね。読書会をやったり、みんなで本を編集してみたり、そういう出会いの場所として機能していくのが大事なのかもしれないですね。自分の好きな古書を自分でダンボールとか木箱に入れて持ち寄って古書市を開催するような取り組みもずいぶん広がっています。一人でいるだけでなく、新しいコミュニケーションが生まれる場所ですかね。
高橋:そうですね。ありがとうございます。名残惜しいですが、お時間になりました。及川さん、お忙しい中本当にありがとうございました。刺激的なお話を聞けてすごく勉強になりました。今後とも懲りずにお付き合いいただけたらと思います。
及川:(笑)もちろんです。花巻に伺った時にはよろしくお願いします。
高橋:本日はありがとうございました。